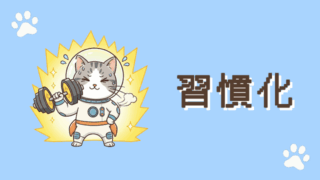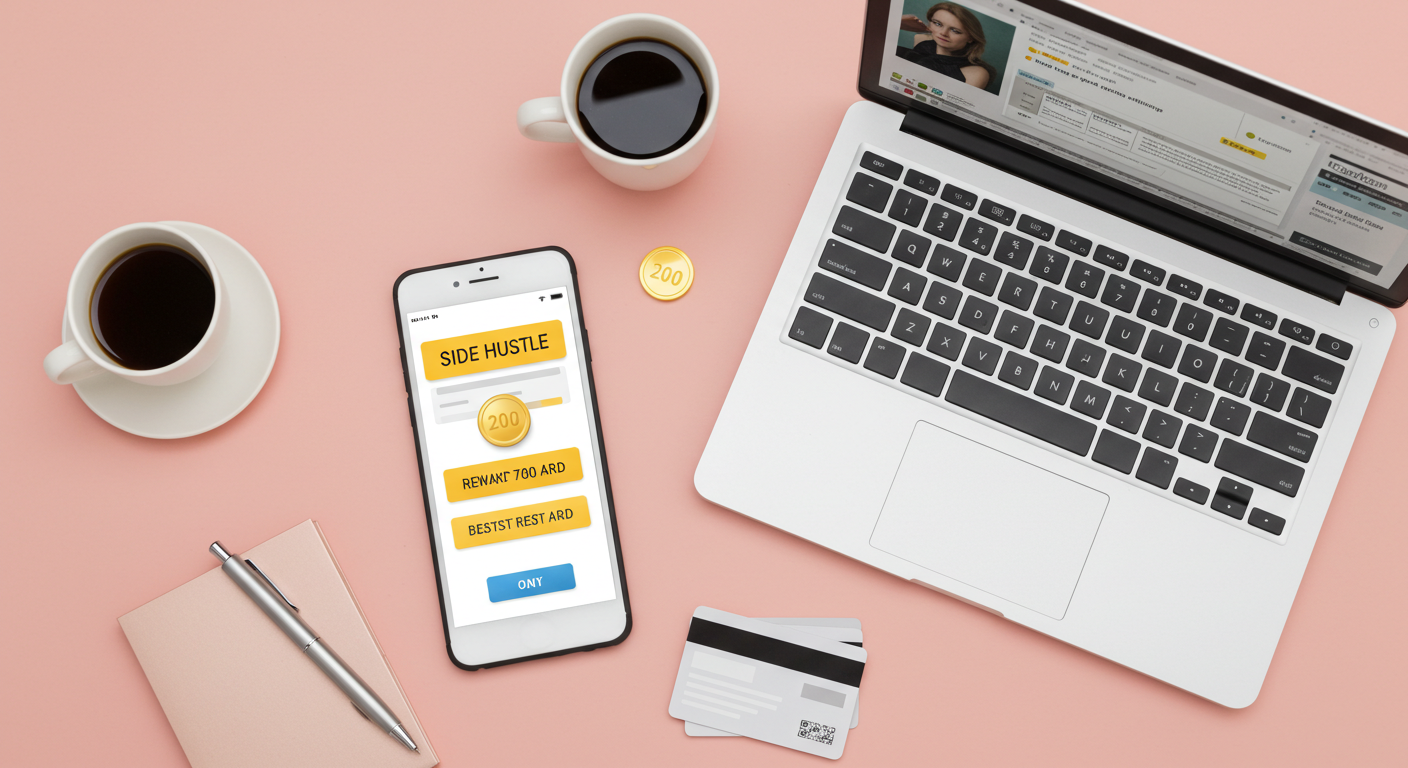会社に勤めながら、AIを使ったブログで副収入を得たい──。
そう思った時に、多くの人が最初につまずくのが「副業が会社にバレないか」という不安です。
収入を増やす目的で始めたのに、会社に知られて立場が悪くなるのは避けたいですよね。
とはいえ、正しい知識を押さえて行動すれば、リスクを最小限にしながら安全にスタートできます。
この記事では、20〜30代の会社員が「AIブログを会社にバレずに始める方法」を、初心者でも分かりやすく解説します。
副業が発覚する3つの原因と、その回避策を具体的にまとめているので、今日から安心して進められるはずです。
■ 副業がバレる最大の理由
副業が会社にバレる原因の多くは 住民税の変化・SNS経由の漏えい・本業への悪影響 の3つです。
ここを押さえて対策すれば、リスクは大きく下げられます。
■ 副業がバレる3つの原因
1. 住民税の金額が変わる
会社は従業員の住民税を給与から天引きしています。
そのため、副業収入が増えると翌年の住民税が上がり、総務・経理が気づくケースがよくあります。
▶ よくあるシーン
-
経理「住民税が急に増えたけど、何かありました?」
-
本人「……(副業のことは言えない)」
これは最も一般的な“バレるルート”です。
2. SNS・人間関係からの漏えい
匿名だと思って投稿した内容が、意外な形で会社に届くこともあります。
▶ よくあるパターン
-
副業アカウントを同僚が偶然見つける
-
仲の良い同僚へ話したことが広がる
-
実名で登録していて検索でヒットする
「自分は大丈夫だろう」と思った瞬間が一番危険です。
3. 本業のパフォーマンス低下
深夜まで作業して睡眠不足になり、仕事の質が落ちると
「もしかして副業…?」
と疑われることがあります。
▶ 見られやすいポイント
-
仕事中の集中力低下
-
遅刻・ミスの増加
-
居眠り
副業よりも本業を優先する姿勢が不可欠です。
■ バレた場合のリスク
会社の規定によって違いますが、以下のようなリスクが考えられます。
-
注意・指導
-
昇給・昇格の停止
-
減給
-
最悪の場合は懲戒処分
「知らなかった」では済まない場合があるため、必ず対策をしておきましょう。
■ 副業がバレないための具体的な回避策
1. 住民税は“普通徴収”に変更する
副業収入を会社に知られにくくするためには、確定申告の際に住民税の徴収方法を 普通徴収(自分で納付)に切り替えるのが効果的です。
▼ 設定すべき項目
-
e-Tax or 確定申告書類の「住民税の徴収方法」
→ 【自分で納付(普通徴収)】を選択
これだけで、住民税が会社に通知されるリスクが下がります。
2. ブログ運営は徹底して“匿名”で
AIブログでも、身元が分かれば意味がありません。
以下は必ず押さえておきましょう。
▼ 匿名運営のチェック項目(WordPress入門者向け)
-
ペンネームを使う
-
プロフィールに個人情報を書かない
-
ブログ専用のメールアドレスを作る
-
ドメインはWHOIS情報を「非公開」に設定
-
SNS用アカウントは副業専用で分離
-
会社のメール・会社のPCは絶対に使わない
AIツールを使う場合も、出力に会社名・本名が紛れないよう注意してください。
3. 作業時間のコントロール
本業への悪影響を避けるために、時間の使い方が重要です。
▼ 時間管理のポイント
-
就業時間外に作業する(通勤中・休憩・夜の短時間)
-
睡眠を削らない
-
体調不良を感じたら即休む
-
会社の端末・ネットワークは使わない
“無理なく続ける”仕組みを作ると、副業の継続率が上がります。
4. 報酬受け取りと確定申告の注意
-
副業の収入は必ず申告
-
報酬の受け取りは個人口座
-
法人名義のアカウントで受け取らない
法律は守りつつ、リスクを最小限にする形が理想です。
■ AIブログと他の副業の比較表(WordPressで使える表形式)
| 副業ジャンル | 特徴 | バレにくさ | AIとの相性 |
|---|---|---|---|
| AIブログ(匿名) | 始めやすい・資産化しやすい | ◎(匿名で運営) | ◎ |
| ポイ活 | スキマ時間に可能 | ◎ | △ |
| スキル販売 | 実績が作りやすい | ○(工夫が必要) | ○ |
| 資産運用 | 手間が少ない | ◎ | △ |
■ AIブログを“安全かつ効率的”に育てるコツ
● テンプレ → 自分の言葉で整える
AIの文章は下書きにぴったりですが、そのまま使うと読者に伝わりにくくなります。
体験談や自分の視点を必ず加えてください。
● 読者の疑問を先回りする
初心者の読者が「これってどうなの?」と感じるポイントを見出しに入れると、検索にも強くなります。
● 図・表・画像で読みやすくする
スマホ読者が多いブログでは、長文よりも「表・箇条書き」の方が理解されやすいです。
WordPressのブロック機能で簡単に挿入できます。
■ よくある質問(Q&A)
【Q1】就業規則で副業禁止。どうすれば?
禁止でも、企業によって運用の厳しさは異なります。
まずは規定を確認し、普通徴収・匿名運営・本業優先の3点を徹底しましょう。
法律面の不安は、専門家に相談すると安心です。
【Q2】AIの文章はそのまま使っていい?
下書きとしては便利ですが、仕上げは必ず自分で。
オリジナリティを入れると検索評価も上がります。
【Q3】確定申告が不安…
税務署や税理士への相談が確実です。
e-Taxを使えば自宅から手続きでき、住民税の設定も簡単です。
■ 今すぐできる5分チェックリスト
-
副業の年間収入をざっくり計算
-
確定申告の「住民税:普通徴収」を設定する準備
-
ペンネーム・専用メール・匿名化を済ませる
-
作業端末を完全に分ける
-
週の作業スケジュールを作成する
■ まとめ
AIブログは、少ない時間でも資産化しやすく、会社員にとって魅力的な副業です。
ただし「住民税」「SNSでの発信」「本業への影響」を軽く見ていると、副業がバレる確率は高まります。
まずは
-
住民税は普通徴収へ
-
徹底した匿名運営
-
本業に支障のない時間管理
この3点をきっちり押さえれば、安心してスタートできます。
今日の行動が、未来の収入源になります。
ムリなく、安全に、小さく始めていきましょう。
AIを活用してブログを始める方法はこちらで紹介してるので参考にしてください。
AIを活用してブログを無料で始める方法|初心者でも効率的に記事を書くコツ